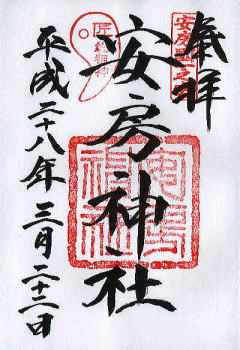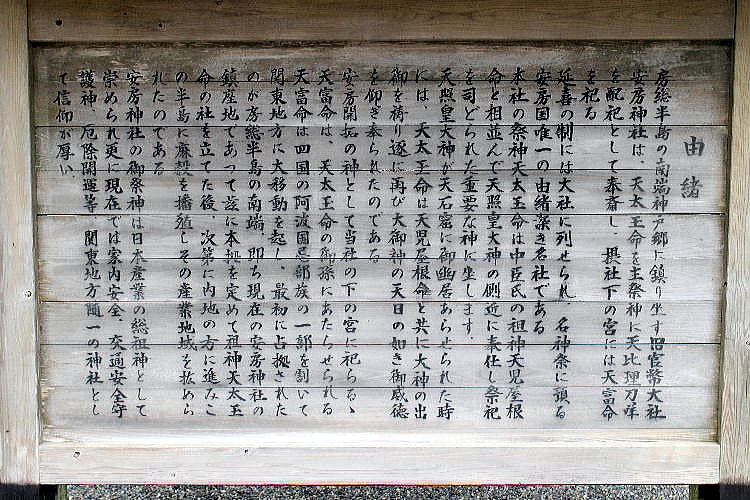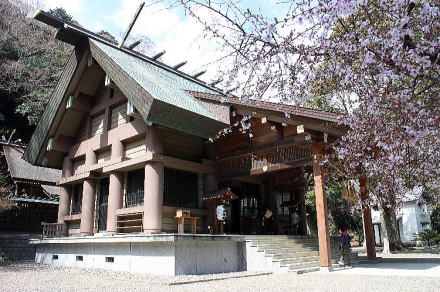| ���ݒn |
��t���َR�s
��_�{589 |
| �ʒu |
�k��34�x55��20.80�b
���o139�x50��12.25�b |
| ��Ր_ |
�V���ʖ� |
| �Њi�� |
�������i���_���j
���[����{
���������
�ʕ\�_�� |
| �n�� |
(�`)�����_���V�c���N |
| �{�a���l�� |
�_���� |
| �ʖ� |
��_�{ |
| ��� |
8��10�� |
| ��Ȑ_�� |
�u�Y�_���i1��14���j
����_���i1��15���j
�_��Ձi12��26���j |