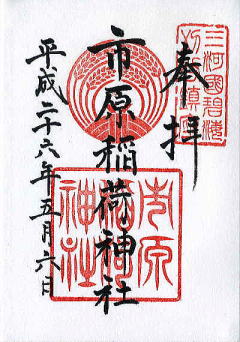白雉4年(653)、亀狭山に瑞兆(ずいちょう…良い事が起こる前兆)が現れ、その地に社殿を創立したのがはじまりと言われています。
その後、天文2年(1533)、水野忠政の刈谷城築城により、現在の場所へ移りました。
永禄3年(1560)、桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれたとき、刈谷城は今川方であった鳴海城代岡部長教の襲撃に遭いました。そのときに市原稲荷神社も焼失しましたが、同5年に再建され初代藩主水野勝成以来の歴代刈谷藩主による寄進を始め、領内3社としての特別な崇敬を受けました。
ご鎮座1350年にあたる平成15年(2003)には、社殿向拝の新築と5色の塗料、社務所の新築、駐車場の新設などの境内整備が行われています。
市原稲荷神社例祭の神賑行事に「神幸祭(神輿渡御祭)」があり、この神輿を護衛するための大名行列が行われます。貞享4年(1687)の大名行列には山車も参加するようになり、この形は今日でも受け継がれています。
大名行列の中で繰り広げられる「奴のねり」は市の無形民俗文化財に指定されています。
昭和40年(1965)以降途絶えていた山車の巡行も、平成14年(2002)には修復された肴町の山車が復活し、平成21年(2009)からは修復された新町の山車も参加するようになりました。最近では子どもたちも加わった山車囃子も賑やかに祭りを盛り上げています。
肴町と新町の山車は小垣江の山車とともに市の有形民俗文化財に指定されています。
例祭のとき、市原稲荷神社の本殿には、初代刈谷藩主水野勝成が奉納したと言われている市指定有形民俗文化財の「獅子頭」が飾られています。