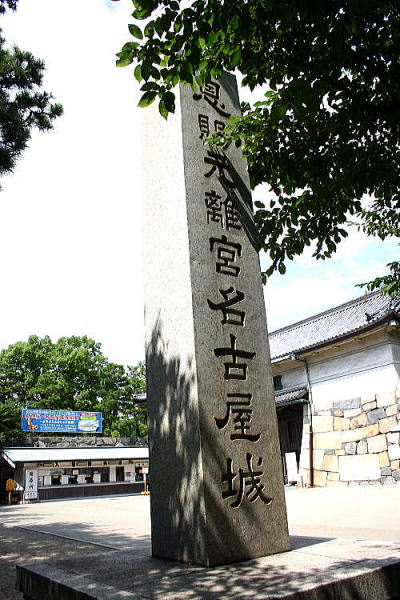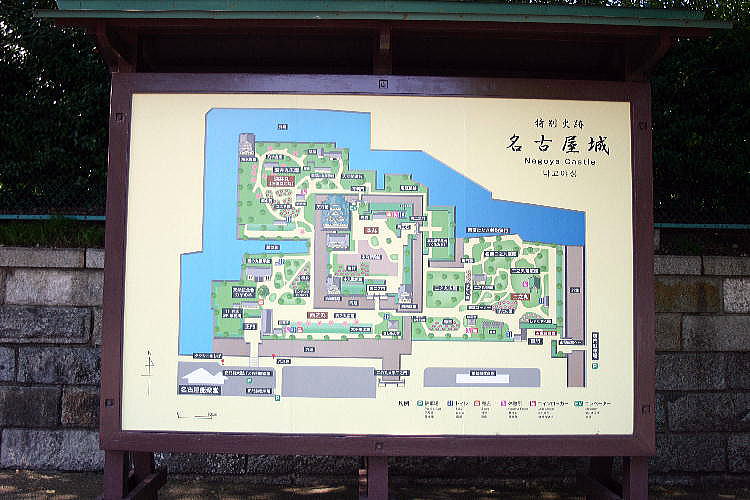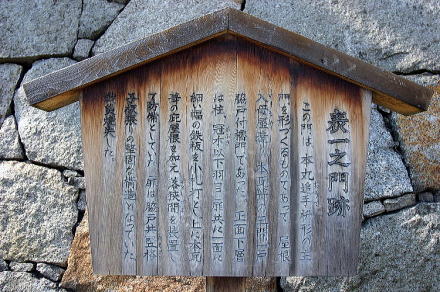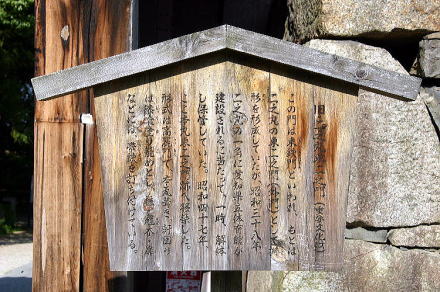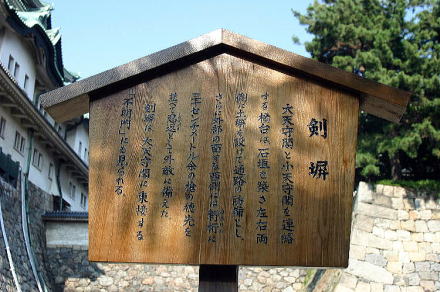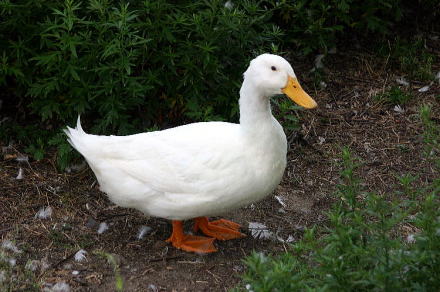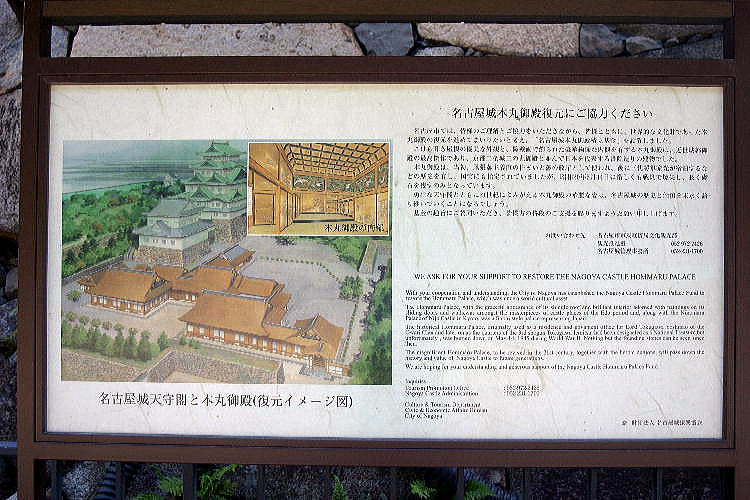| 別名 |
金鯱城、金城、柳城、亀屋城、
蓬左城 |
| 城郭構造 |
梯郭式平城 |
| 天守構造 |
連結式層塔型5層5階地下1階
1612年築 (非現存)
1959年再建(SRC造・外観復元) |
| 築城主 |
徳川家康 |
| 築城年 |
慶長14年(1609年) |
| 主な改修者 |
名古屋城再建委員会 |
| 主な城主 |
尾張徳川家 |
| 廃城年 |
1871年(明治4年) |
| 遺構 |
櫓3棟・門3棟、庭園、石垣、堀 |
| 指定文化財 |
国の重要文化財(櫓3棟、門3棟) |
| 再建造物 |
大小天守、正門、御殿玄関、表書院 |
| 位置 |
北緯35度11分7.77秒
東経136度53分56.71秒 |