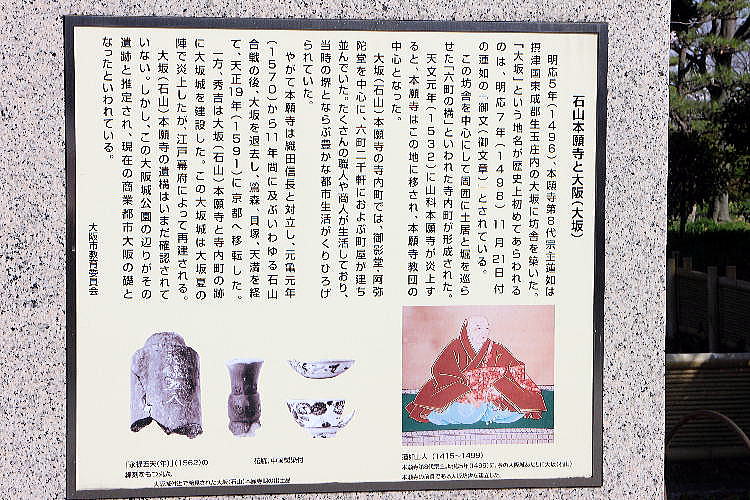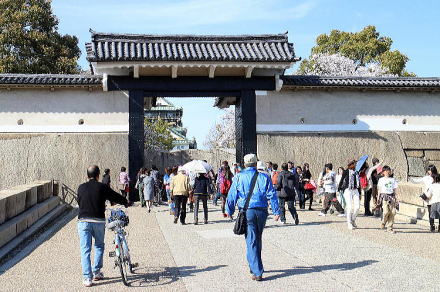| 別名 |
金城、錦城 |
| 城郭構造 |
輪郭式平城または平山城 |
| 天守構造 |
複合式望楼型(豊臣期・1585年築)
独立式層塔型5重5階地下1階(徳川期・1626年再)
いずれも非現存
独立式望楼型5重8階(1931年SRC造復興) |
| 築城主 |
豊臣秀吉 |
| 築城年 |
1583年(天正11年) |
| 主な改修者 |
徳川秀忠 |
| 主な城主 |
豊臣氏、奥平氏、徳川氏 |
| 廃城年 |
1868年(明治元年) |
| 遺構 |
櫓、門、石垣、堀 |
| 指定文化財 |
国の重要文化財(櫓・門など)
登録有形文化財(再建天守)
特別史跡 |
| 再建造物 |
天守 |
| 位置 |
北緯34度41分14.56秒
東経135度31分33.04秒 |